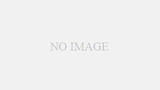地理の授業で出てくる「企業的農業」とは、会社のように経営を重視して行う大規模な農業のことです。
農業といえば家族経営のイメージがありますが、世界には数百ヘクタール以上の広大な農地を機械で管理する「企業的農業」が多く存在します。
この記事では、企業的農業の3つの代表例──企業的穀物農業・企業的牧畜・プランテーション農業──を中心に、それぞれの特徴や分布、利点と課題をやさしく整理します。
企業的農業とは?
「企業的農業」とは、企業のように効率や利益を重視して行う大規模な農業のことを指します。
近代的な機械や技術を導入し、労働力を最小限に抑えて大量生産を行うのが特徴です。家族単位で自給を目的とする農業とは大きく異なり、商業的・輸出志向型の経営が中心です。
家族経営農業との違い
家族経営農業は、家族が中心となって小規模に生産を行い、地域内での消費を目的とすることが多いのに対し、企業的農業は利益を目的とした市場向けの大量生産を行います。
また、経営単位が大きく、資金や機械を投入できるため、生産性が高く、国際市場でも競争力を持ちます。
| 項目 | 家族経営農業 | 企業的農業 |
|---|---|---|
| 経営規模 | 小規模 | 大規模 |
| 経営主体 | 家族 | 会社・企業 |
| 目的 | 自給・地域販売 | 商業・輸出 |
| 労働力 | 家族中心 | 賃金労働者中心 |
| 機械化 | 限定的 | 高度に機械化 |
特徴:大規模・機械化・商業目的・輸出志向
企業的農業の特徴は次の4点にまとめられます。
- 大規模経営
広大な土地を所有・借用し、大量生産を行う。例:数百~数千ヘクタール規模。 - 機械化・省力化
トラクターやコンバインなど大型機械を使用し、少人数で生産。 - 商業目的
市場への出荷・輸出を前提とした経営。自家消費はほとんど行わない。 - 輸出志向
国内市場だけでなく、国際市場での取引を意識した農業経営。
このような形態は、資本力のある企業や農業法人が中心となって行われ、「企業的穀物農業」「企業的牧畜」「プランテーション農業」などに分類されます。
主な分布:アメリカ・オーストラリア・南米・アフリカの一部など
企業的農業は、広大で人口密度が低く、機械化が進めやすい地域に多く分布しています。
代表的な地域を以下に示します。
- アメリカ合衆国:プレーリー(小麦・トウモロコシ・牛の大規模飼育)
- オーストラリア:マリーダーリング盆地(小麦)、グレートアーテジアン盆地(牧畜)
- 南アメリカ:アルゼンチンのパンパ(穀物・牧畜)
- アフリカや東南アジア:熱帯地域のプランテーション(コーヒー・カカオ・天然ゴムなど)
これらの地域はいずれも、広大な土地・機械化のしやすさ・市場との結びつきという条件を備えています。
その一方で、土壌の荒廃・環境破壊・労働問題など、社会的課題も多く指摘されています。
企業的穀物農業の特徴
「企業的穀物農業」は、広大な土地で小麦やトウモロコシなどの穀物を大型機械を使って効率的に生産する農業形態です。
アメリカやオーストラリアなど、広い平原と機械化が進みやすい地域で発達しました。家族単位の農業とは異なり、企業や農業法人が経営し、市場や輸出を目的にした商業的農業が行われています。
主な作物と地域
企業的穀物農業では、主に小麦・トウモロコシ・大麦などの穀物が中心です。これらの作物は、乾燥にある程度強く、機械で大規模に栽培しやすいという特徴があります。
この農業が行われている地域は、年降水量が500mm前後で、穀物の生育に適した黒色土地帯(肥沃な土壌)に多く分布しています。
代表的な地域は次のとおりです。
- 北アメリカのプレーリー(アメリカ・カナダ)
→ 世界最大の小麦・トウモロコシ生産地。 - 南アメリカのパンパ東部(アルゼンチン)
→ 肥沃な草原地帯で、小麦・トウモロコシ・大豆の栽培が盛ん。 - ユーラシアのチェルノーゼム地帯(ウクライナ・ロシア南部)
→ 世界的に有名な黒土(チェルノーゼム)が分布。 - オーストラリアのマリーダーリング盆地
→ 気候が乾燥しており、小麦中心の大規模農業が行われる。
これらの地域はいずれも、広大で平坦な地形・肥沃な土壌・機械化しやすい条件を備えています。
生産方法と特徴
企業的穀物農業では、最新の大型農業機械が活躍します。
トラクター、コンバイン(刈り取り・脱穀を同時に行う機械)、播種機(はしゅき:種まき機)などを組み合わせ、少人数で広大な畑を管理します。
その結果、労働生産性が非常に高く、1人あたりの生産量は家族経営農業の数十倍に達することもあります。
また、生産された穀物は国内市場だけでなく輸出にも回されることが多く、世界の食糧供給を支えています。
ただし、機械や燃料のコストが高いため、資本力のある企業や農業法人が中心となって経営を行っています。
課題と対策
企業的穀物農業の最大の課題は、環境への影響です。
収穫後の畑は作物がなくなるため、裸地(らち)となり、風や雨によって土壌侵食や土壌流出が起こりやすくなります。
この問題を防ぐために行われているのが、次のような対策です。
- 等高線耕作(とうこうせんこうさく)
→ 斜面に対して等高線(高さが同じ線)に沿って畑を作り、雨水の流出を防ぐ方法。 - 防風林の設置
→ 畑の周囲に木を植えて風を和らげ、土壌の飛散を防ぐ。 - 輪作(りんさく)
→ 同じ作物ばかり作らず、豆類などを交互に栽培して土の養分を保つ。
これらの工夫により、環境保全と持続可能な農業の両立が図られています。
企業的牧畜の特徴
「企業的牧畜」は、広大な草原地帯で牛や羊を大規模に放牧して育てる農業形態です。
人の手をあまり加えず、自然の草地を利用して家畜を育てる「粗放的(そほうてき)農業」の代表例といえます。
効率的な肉や羊毛の生産を目的としており、特に乾燥地や半乾燥地で盛んに行われています。
主な地域と飼育動物
企業的牧畜が行われるのは、ステップ気候やサバナ気候など、降水量が少なく農作物の栽培に適さない地域です。
これらの地域では、広い草原に放牧できる土地が多いため、牛や羊を大量に飼育するのに向いています。
主な地域と特徴は次のとおりです。
- アメリカのグレートプレーンズ
→ 牛の放牧が中心。肉牛の肥育も行われ、世界有数の畜産地域。 - アルゼンチンのパンパ西部
→ 牧草地が広がり、牛・羊の放牧が盛ん。牛肉の輸出国として知られる。 - オーストラリアのグレートアーテジアン盆地
→ 広大な乾燥地帯で、羊の飼育(ウール生産)が中心。世界有数の羊毛輸出国。
これらの地域はいずれも、人口が少なく土地が広いという条件を持ち、企業的な経営が成立しやすい環境です。
近年では、効率化のためにGPSやドローンを使った家畜管理も進んでいます。
特徴と課題
企業的牧畜は、自然の草地をそのまま利用する粗放的な農業です。
人手をかけずに大規模経営が可能で、労働生産性が高いという利点があります。
一方で、自然条件に強く依存するため、次のような課題も抱えています。
- 気候変動による影響
乾燥化や干ばつが進むと、牧草が育たず家畜が減少。 - 過放牧による土地の荒廃
家畜が草を食べ尽くすことで、土地が砂漠化しやすくなる。 - 輸送コストや市場価格の変動
広大な地域での輸送が必要なため、経費がかさむ。
こうした問題に対応するため、近年では次のような新しい取り組みも見られます。
- フィードロット(Feedlot)
放牧ではなく、一定期間家畜を柵の中に入れ、トウモロコシなどの飼料を与えて短期間で太らせる方法。
→ 肉質を均一化し、生産効率を高められる。 - 持続可能な放牧管理(ローテーション放牧)
牧草地を区分して順に放牧し、土地の回復を図る方法。
このように、企業的牧畜は経済的な効率性と環境保全の両立を目指して発展しています。
プランテーション農業の特徴
「プランテーション農業」は、熱帯・亜熱帯地域の気候を利用して、特定の作物を大規模に栽培する農業形態です。
企業や外国資本が中心となり、輸出を目的に運営されるのが特徴です。かつては植民地経営の一部として発展し、現在もその名残が見られます。
どんな地域で行われる?
プランテーション農業は、高温多湿の気候が続く熱帯・亜熱帯地域で行われています。
年間を通して気温が高く、雨が多いため、熱帯性の作物がよく育ちます。
主な地域は次のとおりです。
- 東南アジア:インドネシア、マレーシア、フィリピンなど
- アフリカ:コートジボワール、ガーナ、ケニアなど
- 中南米:ブラジル、コロンビア、エクアドルなど
これらの地域では、安定した気候条件と安価な労働力を背景に、企業が大規模に農園を経営しています。
主な作物
プランテーション農業では、主に輸出向けの換金作物が栽培されます。
国内消費よりも、外国への販売を重視した経営が特徴です。
代表的な作物は次のとおりです。
- コーヒー(ブラジル・コロンビア・エチオピアなど)
- カカオ(ガーナ・コートジボワールなど)
- 綿花(インド・エジプトなど)
- 天然ゴム(マレーシア・タイなど)
- バナナ(フィリピン・エクアドルなど)
- パーム油(マレーシア・インドネシアなど)
これらの作物は、主にモノカルチャー(一種類の作物を集中栽培する方法)で生産されます。
効率的な反面、病害虫の被害や価格変動のリスクが高いという問題もあります。
経営の特徴と課題
プランテーション農業は、企業が中心となって経営する大規模農業です。
植民地時代にヨーロッパ諸国が現地で開発した農園が起源であり、現在も外国資本の企業が経営している場合が多く見られます。
- 経営の特徴
・企業が土地と資金を持ち、労働者を雇って生産
・安い労働力を利用し、輸出による利益を重視
・大部分が外国企業または多国籍企業による運営 - 主な課題
・価格変動の影響:国際市場の価格が下がると、現地農民の収入が激減
・労働環境の問題:低賃金・長時間労働が問題視されることもある
・環境破壊:森林伐採や土壌劣化など、自然環境への影響
これらの問題を解決するために、フェアトレード運動や環境に配慮した認証制度(例:RSPO認証)が広がりつつあります。
企業的農業のまとめとこれから
企業的農業には、次の3つの形態がありました。
- 企業的穀物農業:小麦・トウモロコシなどを機械化で大量生産
- 企業的牧畜:牛や羊を広大な草地で放牧
- プランテーション農業:熱帯で輸出用作物をモノカルチャー栽培
これらに共通するのは、
👉 大規模・機械化・輸出志向の農業形態であるという点です。
ただし、環境問題や労働問題などの課題も多く、今後は以下のような方向が重視されます。
- 環境への配慮(SDGs):森林保全・土壌保全・水資源の保護
- 持続可能な農業:過放牧や過剰栽培を防ぎ、資源を守る
- フェアトレード:生産者の生活を守り、適正な取引を行う
企業的農業は、世界の食料供給を支える一方で、地球環境や人々の生活とどう共存するかが今後の大きな課題といえるでしょう。