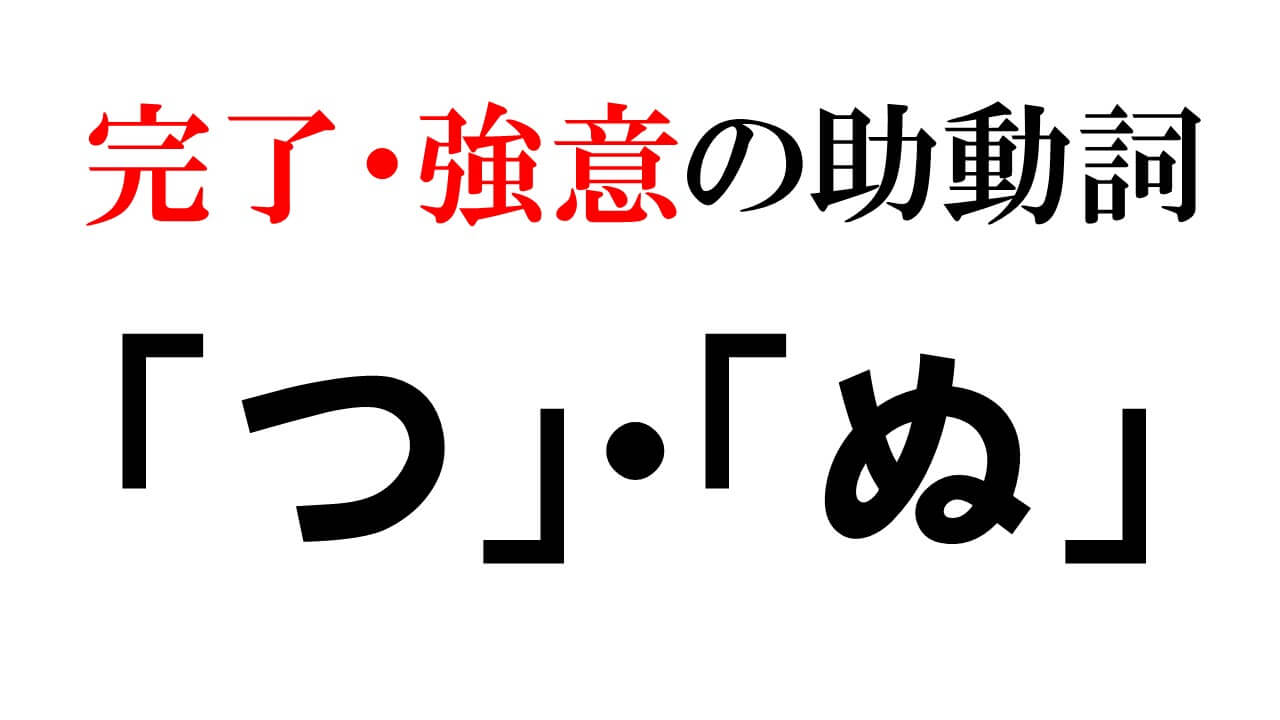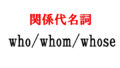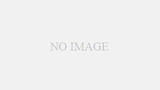古典文法を勉強していると必ず出てくるのが 助動詞「つ」「ぬ」 です。どちらも「完了」と「強意」という2つの意味を持っています。
本記事では、助動詞「つ」「ぬ」の 接続・活用の形、2つの意味である 「完了」「強意」 の違い、そして実際の 例文と訳し分けのコツ をわかりやすく解説します。
「つ」と「ぬ」がわかると、古文読解がぐっと楽になります。テスト対策にも、社会人の学び直しにも役立つ内容ですので、ぜひ最後まで読んで理解を深めていきましょう。
助動詞「つ」「ぬ」とは?
助動詞「つ」「ぬ」は、どちらも「完了」と「強意」という2つの意味を持ち、似たように使われます。
ここではまず、「つ」「ぬ」がどんなときに使われる助動詞なのか、そして接続の形(活用語にどう続くか)や活用の種類を整理しておきましょう。
どんなときに使う助動詞?
「つ」「ぬ」は、いずれも動詞などの 連用形 につき、次の2つの意味を表します。
- 完了(〜てしまう)
→ 動作がすっかり終わったことを表す。
例:花の色も移りにけり(=移ってしまった) - 強意(きっと〜だろう)
→ 動作を強く言い切るニュアンス。とくに下に推量の助動詞「む」「べし」などが続くと、この意味になることが多い。
例:必ず成し遂げてむ(=きっと成し遂げてみせる)
「つ」と「ぬ」は連用形接続
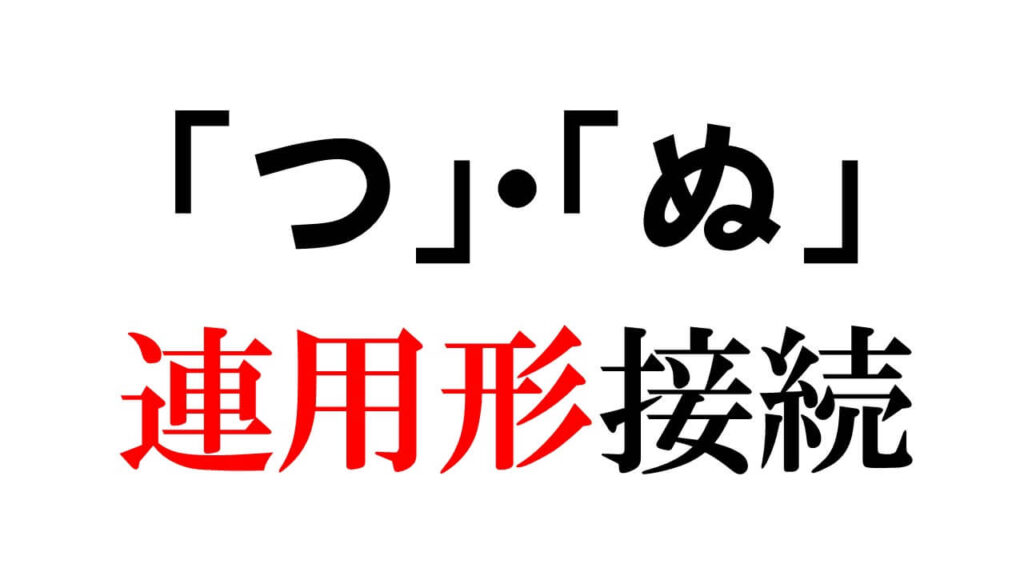
- 接続:どちらも 連用形 に付く。
例: - 「咲き つ」…「咲く(四段活用)の連用形+つ」
- 「行き ぬ」…「行く(カ行四段活用)の連用形+ぬ」
活用の種類|「つ」は下二段型、「ぬ」はナ行変格型
助動詞にもそれぞれ活用のしかたがあります。ここでしっかり整理しておきましょう。
「つ」の活用(下二段型)

| 未然形 | 連用形 | 終止形 | 連体形 | 已然形 | 命令形 |
|---|---|---|---|---|---|
| て | て | つ | つる | つれ | てよ |
例:書き て、書き つ、書き つる
「ぬ」の活用(ナ行変格型)
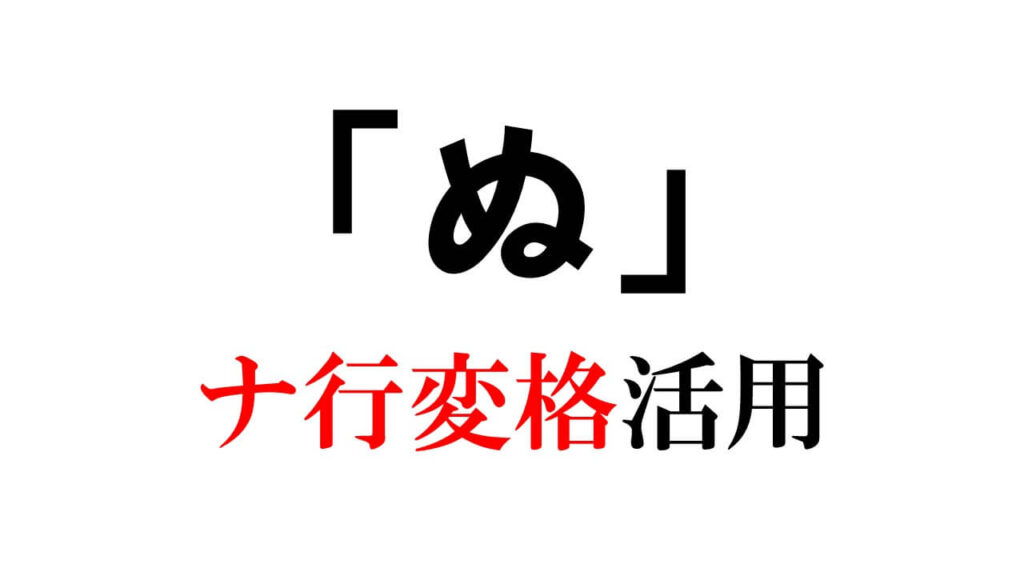
| 未然形 | 連用形 | 終止形 | 連体形 | 已然形 | 命令形 |
|---|---|---|---|---|---|
| な | に | ぬ | ぬる | ぬれ | ね |
例:読み ぬ、読み にけり、読み ぬる
👉 どちらも形は似ていますが、活用の種類が違うことに注意。
- 「つ」=下二段活用(動詞と同じように変化)
- 「ぬ」=ナ行変格活用(特殊な変化をする)
意味と用法|完了と強意
助動詞「つ」「ぬ」は、どちらも2つの意味を持っています。「完了」と「強意」です。
完了の意味(〜てしまう)
動作や状態がすでに完了していることを表します。現代語の「〜してしまった」と訳すと分かりやすいです。
📖 例文
花の色は うつり にけり いたづらに(小野小町『古今和歌集』)
→ 花の色はすっかり色あせてしまった。
ここでは「にけり」が「完了+過去」を表し、花の色がすでに失われたことを示しています。
強意の意味(きっと〜する/ぜひ〜してしまう)
「つ」「ぬ」が下に推量の助動詞(む・べし など)をともなうとき、動作を強く強調する意味になることが多いです。
📖 例文
今はただ思ひ絶え なむ(『伊勢物語』)
→ 今はただ思いを絶ってしまおう。
(「なむ」は「ぬ」+「む」。ここでは「必ず〜してみせる」という強い決意を表す)
👉 見分け方のコツ:
- 直後に推量の助動詞「む」「べし」などがあると強意
- そうでなければ多くは「完了」と考える
例文で確認しよう
ここでは実際の古文の例文を通して、助動詞「つ」「ぬ」がどのように使われているかを見ていきましょう。
助動詞「つ」の例文と解説
① 完了の用法(〜てしまった)
花の色も移り にけり(小野小町『古今和歌集』)
- 「咲きて(=咲いて)」+「つ」+「けり」
- 「つ」は完了を表し、花の色がすっかり変わってしまったことを示している。
② 強意の用法(きっと〜だろう)
必ず成し遂げ つべし
- 「つ」+「べし」
- 「つ」が強意、「べし」が推量。
- 訳:「必ず成し遂げるだろう」
助動詞「ぬ」の例文と解説
① 完了の用法(〜てしまった)
人ごとにいさめ ぬれば、つひにやみにけり(『大鏡』)
- 「いさめ ぬ」=いさめてしまった
- さらに「けり」が付いて「やめてしまったのだ」という意味。
② 強意の用法(きっと〜だろう)
いと心細く覚え ぬ べし(『源氏物語』)
- 「ぬ」+「べし」
- 強意+推量で「きっと心細く思うだろう」という訳になる。
「つ」「ぬ」の違いを比較してみよう
| 助動詞 | 活用の種類 | 接続 | 意味 | 例文(訳) |
|---|---|---|---|---|
| つ | 下二段型 | 連用形 | ①完了=〜てしまう ②強意=きっと〜する | 咲き つ(咲いてしまった) 成し遂げ つべし(きっと成し遂げるだろう) |
| ぬ | ナ行変格活用 | 連用形 | ①完了=〜てしまう ②強意=ぜひ〜する | いさめ ぬ(いさめてしまった) 覚え ぬべし(必ず思うだろう) |
👉 まとめ
- 接続はどちらも 連用形
- 活用の種類が違う(つ=下二段、ぬ=ナ変)
- 意味は同じ「完了」「強意」だが、訳し分けは文脈や後ろに来る助動詞で判断する
「つ」と「ぬ」の覚え方のコツ
助動詞「つ」「ぬ」は、どちらも接続は連用形、意味は完了と強意という共通点をもちます。
そのため、助動詞の中では割と覚えやすいほうだと思います。それでも一応、覚えやすくする工夫を紹介します。
セットで覚えると混乱しない
「つ」と「ぬ」はどちらも同じ意味(完了・強意)を表すので、バラバラに覚えるより、まとめて一緒に覚えるほうが効率的です。
✅ 接続:どちらも 連用形 に付く
✅ 意味:どちらも 完了(〜てしまふ)・強意(きっと〜する)
👉 この2つをペアにして、
- 「つ・ぬはセット!連用形につく!」
と口ずさむだけでも、テストで思い出しやすくなります。
下に推量の助動詞があれば強意
「つ」「ぬ」は、推量の助動詞(む・べし など)が後ろに来たら『強意』になることが多いです。
例えば、
- 「必ず勝ち つべし」=必ず勝つだろう
- 「思ひ出で ぬらむ」=きっと思い出すだろう
強意を見分けるコツは、
- 「む」「べし」などの推量とセットかどうかを確認する
- 強意のときは訳に「きっと」「ぜひ」など強い気持ちの言葉を入れる
これを意識すると、完了と強意の区別がぐっと簡単になります。
関連する助動詞もチェック!
「つ」「ぬ」と同じように 完了の意味 を表す助動詞には、ほかにも種類があります。
- たり(完了・存続)
- 例:花の咲き たり(=花が咲いてしまった/花が咲いている)
- り(完了・存続)
- 例:門に立て り(=門に立っている)
👉 これらは「つ」「ぬ」と同じ「完了」を表すけれど、接続の形やニュアンスが少し違うのがポイントです。
本記事では詳しくは扱いませんが、気になる人は以下の記事も参考にしてください。
➡️ [助動詞「たり」「り」の意味と使い分けを解説(別記事リンク)]
まとめ|助動詞「つ」「ぬ」は完了と強意を押さえれば怖くない
- 「つ」「ぬ」は両方とも連用形に付く助動詞
- 「つ」は下二段型、「ぬ」はナ行変格型
- 意味は共通して 「完了(〜てしまふ)」「強意(きっと〜する/ぜひ〜する)」
- 推量の助動詞(む・べし など)が続くと強意になる ことが多い
- 「たり」「り」も似た意味をもつので、あわせて覚えると理解が深まる
👉 ポイントは「つ・ぬはセットで覚えること」です。
試験では訳を迷うことが多いですが、「完了か強意かは文脈と後ろの助動詞で判断」と押さえておけば安心です。