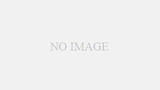九州地方は、温暖な気候と豊かな自然に恵まれ、日本でも農業と工業のどちらもさかんな地域です。
筑紫平野の二毛作や宮崎平野の促成栽培など、地域の気候や地形を生かした特色ある農業が行われています。一方で、明治時代の八幡製鉄所から始まった北九州工業地域を中心に、自動車産業や半導体産業などの新しい工業も発展してきました。
また、かつては洞海湾の水質汚濁や水俣病などの公害問題も起きましたが、現在では環境対策が進み、「自然と産業が共に発展する九州」として新たな姿を見せています。
この記事では、九州地方の農業と工業の特徴、発展の歴史、そして環境への取り組みをわかりやすく解説します。
九州地方の農業の特徴とは?
九州地方は、気候と地形の両方に大きな特徴があります。
まず、温暖で雨が多いことから、米や野菜、果物の栽培に適しています。
また、筑紫平野・熊本平野・宮崎平野などの広い平野がある一方で、シラス台地のように火山灰が積もった土地もあります。
このような環境の違いに合わせて、地域ごとに異なる農業が発展してきました。
平野では稲作や野菜づくりが盛んに行われ、山地や台地では畜産が中心となっています。
筑紫平野の二毛作|米と麦を組み合わせた効率的な農業
福岡県や佐賀県に広がる筑紫平野は、九州地方で最も広い平野です。
ここでは、「二毛作(にもうさく)」と呼ばれる農業が行われています。
二毛作とは、同じ土地で一年に二回、違う作物を育てる方法のことです。
筑紫平野では、
- 夏の「表作(メインとして作る作物)」には稲(米)を育て、
- 冬の「裏作」には小麦や大麦を育てます。
このように季節に応じて作物を変えることで、土地を無駄なく使い、農業の収入も増やすことができます。温暖な九州だからこそできる、効率的で理にかなった農業といえるでしょう。
福岡・熊本の園芸農業|ブランド化された果物と野菜
九州では、都市の周辺で行われる園芸農業も盛んです。
これは、都市に近い場所で野菜や果物、花などを栽培し、新鮮な状態で出荷できるという利点があります。
- 福岡市周辺では、いちご「あまおう」が有名です。
「あまい・まるい・おおきい・うまい」の頭文字から名づけられたブランドいちごで、全国でも人気があります。 - 熊本平野では、トマトの栽培が盛んです。ハウス栽培によって一年中安定した出荷ができるようになっています。
こうしたブランド化・高品質化の取り組みは、農業の新しい形として全国に広まっています。
宮崎平野の促成栽培|冬でも早く出荷できる仕組み
九州南部の宮崎平野では、促成栽培(そくせいさいばい)がさかんです。
促成栽培とは、ビニールハウスなどで温度や湿度を調整し、出荷時期を早める栽培方法です。
宮崎では、冬でも温暖な気候を生かして、
- きゅうり
- ピーマン
などを早い時期に出荷しています。
これにより、寒い地域ではまだ取れない時期に野菜を市場に出せるため、高い値段で売ることができるのです。
促成栽培は、農家の収入を安定させる工夫の一つとなっています。
鹿児島・宮崎の畜産業|シラス台地を生かした経営とブランド化
九州南部の鹿児島県や宮崎県では、畜産業がとても盛んです。
この地域には、火山の噴出物が積もってできたシラス台地が広がっており、水はけがよい反面、稲作には向いていません。そのため、広い土地を利用して牛や豚、鶏の飼育が発展しました。
代表的なブランドには、
- 鹿児島黒牛
- 宮崎牛
- かごしま黒豚
などがあります。
また、海外からの安い輸入肉に負けないように、
- 大規模化して効率的に飼育する
- ブランド化して高品質で販売する
などの工夫が進められています。
こうした努力によって、九州の畜産は日本有数の産地として知られています。
大分県の一村一品運動|地域の特産を全国へ
九州地方の農業を語るうえで欠かせないのが、大分県の一村一品運動です。
これは、「それぞれの村や町が、自分たちの特産品を1つ決めて育てよう」という取り組みです。
大分では、
- しいたけ
- かぼす
などが有名で、全国的なブランドになりました。
一村一品運動は、地域の農業を活性化させるとともに、観光や地産地消(地域で作って地域で消費する)にもつながっています。現在では、日本各地や海外にも広まっており、地域づくりの成功例として知られています。
九州地方の工業の特徴
北九州工業地域
九州地方で最も早く工業が発展したのが北九州工業地域です。明治時代、八幡製鉄所(やはたせいてつしょ)が建設され、日本の近代的な鉄づくりが始まりました。筑豊炭田(ちくほうたんでん)でとれる石炭を使って鉄を生産し、日本の産業を支える中心地となりました。
しかし、昭和30年代になると、エネルギーの中心が石炭から石油へと変わる「エネルギー革命」が起こります。これにより石炭の需要が減り、北九州の鉄鋼業も衰退しました。
その後は、公害の問題(洞海湾の水質汚濁など)を解決しながら、環境産業やリサイクル工場などに転換。現在は、環境保全と共生する「新しい工業地域」として再生しています。
自動車工業の発展
近年の九州では、自動車工業がめざましく発展しています。
特に福岡県にはトヨタ・日産などの大規模な自動車工場が進出し、「日本の自動車生産の一大拠点」となっています。また、熊本県にはホンダのバイク工場があり、部品メーカーも集まることで地域の雇用を支えています。
このように九州は、交通の便のよさや港湾施設の充実、海外(アジア)との近さを生かして、自動車関連産業が盛んになっています。
IC産業(半導体産業)の発展
九州では、コンピューターやスマートフォンに欠かせないIC(集積回路)や半導体の工場も多く立地しています。
その代表が、TSMC(台湾積体電路製造)の熊本工場です。
熊本県菊陽町(きくようまち)に建設されたこの工場では、国内外の企業が協力して最新の半導体を生産しています。
このように、九州は「シリコンアイランド九州」とも呼ばれるほど、電子工業が発展しています。
まとめ
九州地方の工業は、かつての重工業中心から、環境・自動車・電子といった新しい分野へと移り変わっています。歴史ある北九州工業地域が再生し、最新技術の拠点も増えることで、九州は日本の「新しい産業の中心地」になりつつあります。
九州地方の公害問題と環境対策
洞海湾の水質汚濁(どうかいわんのすいしつおだく)
かつての北九州工業地域では、日本の近代化を支えるために多くの工場が建ち並びました。
鉄鋼業や化学工業がさかんになったことで、洞海湾(福岡県北九州市)は「鉄の海」と呼ばれるほどの水質汚濁(すいしつおだく)に苦しみました。
工場からの排水によって海が黒くにごり、魚や貝がほとんどすめない状態になってしまいました。
当時は「公害(こうがい)」という言葉もあまり知られておらず、経済の発展が優先されていた時代です。
しかしその後、市民の声や行政の努力により、環境改善の取り組みが進められました。
工場排水の処理施設が整備され、企業も環境対策を行うようになりました。
今では洞海湾の水質は大きく回復し、魚も戻ってくるほどになっています。
→ 北九州市は現在、「環境モデル都市」として、世界に向けて公害克服の経験を発信しています。
水俣病(みなまたびょう)|熊本県の公害
もう一つ、九州地方で忘れてはならないのが水俣病です。
これは1950年代に熊本県水俣市で発生した深刻な公害病です。
原因は、化学工場から流された有機水銀を含む排水でした。
この有害な物質が魚や貝にたまり、それを食べた人々が神経の異常などの症状を起こしました。
手足がしびれる、言葉が出にくくなる、視野がせまくなるなど、深刻な健康被害が多くの人に広がりました。
当初は原因が特定されず、被害が長く放置されてしまったことも大きな問題でした。
のちに国と企業が責任を認め、補償と再発防止の取り組みが進められました。
環境保全への教訓
これらの公害問題は、「経済の発展だけを追い求めると、人や自然が傷つく」という大きな教訓を残しました。
その後、日本では公害防止法の制定や環境基準の強化が進められ、全国で環境保全の意識が高まりました。
現在の九州では、
- 環境に配慮した工場運営
- 再生可能エネルギーの導入
- ごみや資源のリサイクル
など、「人と自然が共に生きる地域づくり」が進められています。
九州の公害問題は、かつての失敗を乗り越えながら、「汚染から再生へ」という希望の道を歩んできました。
まとめ|自然と産業が共に発展する九州へ
九州地方は、温暖な気候と豊かな自然環境をいかした農業に加え、近代以降は工業の発展によって日本経済を支えてきました。
明治時代には八幡製鉄所を中心に重工業が栄え、現代では自動車や半導体など、高い技術力をもつ新しい産業が成長しています。
一方で、洞海湾の水質汚濁や水俣病のような公害問題も経験しました。しかし、それらの経験を通じて人々は環境の大切さを学び、企業・自治体・市民が協力して持続可能な社会づくりを進めています。
現在の九州は、
- 環境に配慮したものづくり
- 再生可能エネルギーの導入
- 地域の特産品を生かした産業振興
といった取り組みを重ねながら、「自然と産業が共に発展する地域」を目指しています。